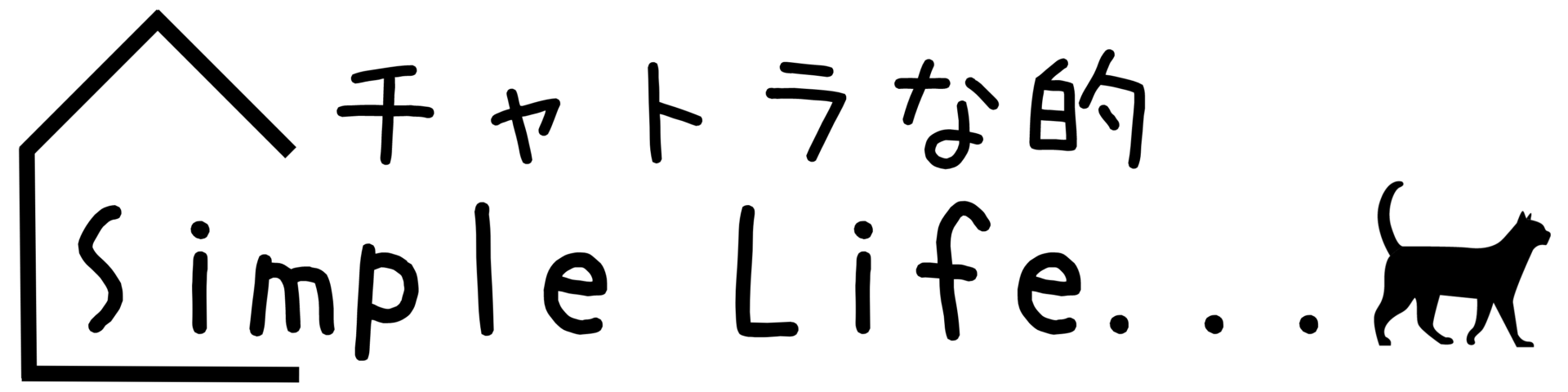親や祖父母の家を相続したものの、使う予定もなく空き家のまま・・・
「思い出があるから壊したくない」「いずれ誰かが住むかも」と先送りにしているうちに、家は急速に傷み始めます。
古民家は人が住まなくなると驚くほど劣化が早く、管理を怠れば固定資産税の負担まで増える可能性があります。
この記事では、実際に古民家の改修・売却を経験した立場から、空き家を相続したあとに気を付けたいポイントを解説します。
空き家は「築年数」より「空き家期間」が劣化を左右する


古民家の価値を判断する際、多くの方が築年数に目を向けますが、実際に重要なのは「どれだけ空き家だったか」という点です。
家というのは、人が暮らしてこそ湿度や温度が保たれ、木材や壁が呼吸できる構造になっています。
逆に誰も住まなくなると、換気が止まり、湿気がこもってカビやシロアリが発生しやすくなります。
私の経験では、3年以上空き家になっている古民家は修繕コストが一気に上がる傾向があり、特に北国など湿度や寒暖差が大きい地域では、たった一冬越しただけで屋根や柱が傷んでしまう例もあります。
「築年数より空き家年数が劣化の指標になる」という意識を持つことが大切です。
残地物は基本的に“無価値”。親族の家でも早めの整理を


相続した古民家には、家具や電化製品、日用品などがそのまま残っていることが多いものです。
しかし実際に価値のあるものは、すでに他の家族が持ち出しているケースがほとんどで、残っている荷物は汚損・劣化していて再利用できないことが多いのが現実です。
処分には想像以上の手間と費用がかかり、依頼する業者によっては10万円単位の差が出ることもあります。
そのため、売却を考えている場合はできるだけ早い段階で整理を進め、残地物を残さない状態にしておくことが理想です。
残された荷物が多い家は、見た目の印象が悪く、買い手の関心を大きく下げてしまいます。
また、残地物があることで査定額が下がったり、買取を断られることもあります。
売却をスムーズに進めたいなら、「思い出の品」と「不要な物」をしっかり仕分けして、できる限り空の状態にしておくことが重要です。
 みやかつ
みやかつ残地物の処分は“後回し”にしない!!
早めに片付けるほど、売却がスムーズに進みます。
売却判断は早いほど得策




空き家は放っておいても良くなることはありません。
時間が経つほど建物は劣化し、修繕費が増え、結果として売却価格は下がっていきます。
「まだ使えるから」「いつか誰かが住むかもしれない」と考えて先延ばしにすると、最終的には買い手が見つからず、解体費用だけが残るケースも少なくありません。
相続後は早めに不動産会社や買取業者に相談し、売却か活用かの方向性を定めることが大切です。
空き家問題は“決断の早さ”が鍵になります。



古民家の売却はワケガイがおすすめです。
他で買取を拒否された物件でも諦めずに査定依頼を出してみましょう!!
詳しくは下のバナーからどうぞ。
固定資産税は年々重くなる
空き家をそのままにしておくと、思わぬ税金負担がのしかかります。
管理が不十分な状態が続くと「特定空家」に指定され、住宅用地の軽減措置が外れてしまうため、固定資産税が最大で6倍近く跳ね上がることがあります。
つまり、「持っているだけで損をする家」になってしまうのです。
古民家を維持するにしても、定期的な換気・掃除・草刈りなどの最低限の管理は欠かせません。
古民家の買取は業者選びが肝心
古民家のような古い物件を買い取ってくれる業者は限られています。
たとえば、買取実績が多い業者でも実際に取引できるのは全体の約1割程度と言われています。
「問い合わせたけど断られた」という話も珍しくありません。
このため、1社だけに頼らず、必ず複数の買取業者に査定を依頼することが大切です。
査定額や条件は業者によって大きく異なるため、比較検討が売却成功の鍵になります。
最悪の場合は解体も選択肢に




もし建物の傷みが激しく、修繕よりも解体した方が合理的と判断される場合もあります。
古民家を取り壊して更地にすると、土地としての価値が見直され、売却がスムーズになるケースも多く見られます。
ただし、解体には高額な費用がかかるため、必ず複数の解体業者に見積もりを取ることが重要です。
見積額には業者ごとに大きな差があり、10万円以上の違いが出ることもあります。



解体業者を選ぶのは大変ですが解体工事110番なら条件にあう解体業者を即時に選定してくれます。
解体工事110番へは、下記のバナーからどうぞ。
まとめ
古民家を相続したとき、最も避けたいのは「何も決めずに放置すること」です。
時間が経つほど建物は劣化し、残地物が増え、税金負担が重くなります。
最終的に「売れない・壊すしかない」となる前に、早めに動くことが何よりの対策です。
残地物の整理、複数業者への相談、必要であれば解体まで視野に入れ、現実的な選択を進めていきましょう。
大切なのは「思い出を守るために、決断を先延ばしにしない」こと。
それが、古民家を次の世代につなぐ第一歩です。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。